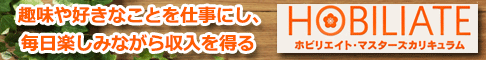ハルオサンの「警察官くびになってからブログ」が、角川より書籍化することになったそうです。
おめでとうございます!
今日夢を見ました。
大学のラグビー部の時の夢です。
夢の中で私はスパイクを忘れてしまいます。スパイクがないと練習に参加できません。私は焦ってスパイクを探し回りました。
そしてテーブルには「労働マルチ」時代のノリさんが座っていました。
夢自体にオチはないです。
ただラグビーしていたころの思い出と、労働マルチのブラック企業の思い出が重なって出てきただけの話です。
私が以前働いていた会社は、ハルオサンがトップセールスでも月5万円しかもらえなかった超ブラック企業でした。2016年現在では報酬面に関してはだいぶ改善がみられたようで、トップセールスであれば日に2万円とか持って帰る人もざらでした。
ただし、「労働マルチ」という呼称がつくように、いわゆるネズミ講のような、商品売買を介して親が利益を得るという仕組みを、労働力を介して親が利益を取るという仕組みに巧みに置き換えたブラック企業であることは間違いありません。
単純に言うと労働力を提供する労働者を増やし、増えたところで会社そのものを分裂させ、またそこで労働力を集める、といったことを繰り返していく、という仕組みです。
私が勤めていたブラック企業のサイトを今見てみると、当時は2社だけだったのに、今は5社に増殖していました。増殖した中で働いている彼らはある意味楽しそうです。
搾取してお金をたくさんもらう人間が目の前で殖えていき、いつか自分もこの人たちのように搾取する側に回れるというモデルケースが現実のものとして眼前で繰り広げられているからです。
おそらくこういった類の「誰かから搾取して少数の人間が莫大な利益を得る」という形の会社はなくなることはないでしょう。
ハルオサンの本がとても売れて、労働マルチという仕組みに視線が向けられ、皆が注目するようになっても、この会社はおそらく消滅することなく、搾取の仕組みを進化させながらしたたかに生き残っていくことになるでしょう。
しかし、私はこの労働マルチのブラック企業がなくなればいい、とは思っていません。なぜならば、そこには夢があるからです。現実のモデルケースとして目の前に大金を得ている人がいて、自分もそこに入れる道を今歩いている、という夢です。
目の前で繰り広げられているだけに、それはそこで搾取されている側にとっては確かな夢なのです。夢というか、つかめそうな現実、実現しそうな夢です。
この人たちはある意味幸せです。
希望を持っているからです。
村上龍は「希望の国のエクソダス」という小説の中で、強大な影響力を持った中学生にこう言わせます。
「この国にはなんでもある。でも希望だけがない」
希望がないと人間は生きていけません。
「週休1日とか生きている意味がない」というブログを読みましたが、生きている意味がない、とはイコール希望がない、という意味です。
私はこの自分のブログを書いていて、最も参考にしているのはハルオサンのブログです。
ハルオサンのブログは単純に読んでいて面白い。まあだから書籍化に至ったわけですが。ハルオサンの歩んできた人生がブログに書かれている通り、本当に波乱万丈でおもしろいかどうかは関係ありません。ハルオサンのブログが事実かどうかはどうでもよくて、ただ単に読んでいて面白い。
私はハルオサンのブログから「おもしろいブログ(読み物)」を書けばいいんだ!こういうものを書きたい!自分の人生をさらして。と思っていましたが、それは大きな間違いでした。
たいしておもしろくもない事実をおもしろく読ませるスキルがある人がいる。逆にものすごいおもしろい事実があるのに、まったくおもしろくなくしか書けない人もいる。
現段階では私は間違いなく後者です。
ハルオサンのブログ書籍化という事実は、ブログで金を稼ごうとしている人にとってはひとつの成功、到達点です。
私は単純にハルオサンのブログ書籍化という事実に「いいなー」という感想を抱きました。そして「おれも本出したいなー」と思いました。
しかし私のブログは今のままでは本にはならないでしょう。
エンターテイメントも情報も提供しきれていないからです。
はっきりいってつまんないからです。
ハルオサン、ブログ書籍化おめでとうございます。
私はハルオサンのブログ書籍化という事実を踏まえて、もう一度自分のブログを見なおしていきたいと思います。
私はこのブログで一体何がしたいのか、もう一度それを明確にしていきます。
書籍化なのか、マネタイズなのか。それとも失速して興味を失い辞めてしまうのか。
日々ブラック企業の社畜として、現在20連勤中の私にはあまりブログに注力する時間が取れません。
それでも明確な目標を掲げて、それを現実にするために、何かを切り捨ててブログに向かうことができるのか。
もう一度仕切り直しです。
ちなみに私はこのお話がお気に入りです。
おしまい
いちばん読まれている記事